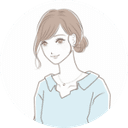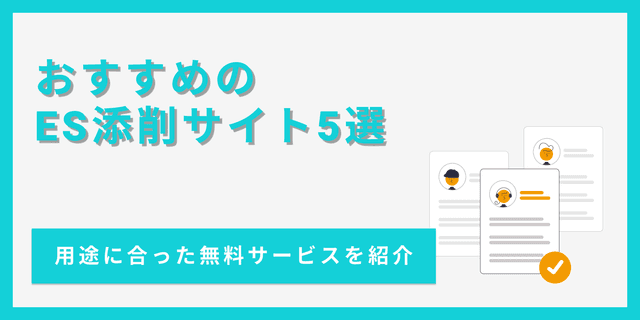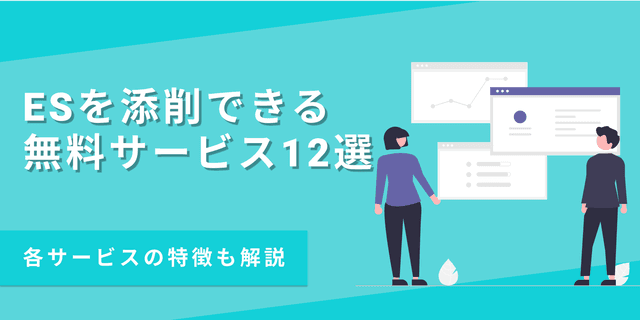完全無料26.27卒必見!
ES作成に役立つおすすめツール3選!
あなたの魅力を最大限に引き出すESがわずか60秒で完成します
あなたのESを入力するだけでAIが即座に採点しフィードバックが受けられます
自己PRとは何かから他者と差別化する方法まで詳しく解説します
ESでは自己PRや志望動機とは別に、「ゼミの活動内容」を書く必要があります。ゼミは学生時代に興味・関心のあった分野を明確に表すため、企業はそこから就活生の個性を知りたいと考えています。
企業の意図を理解して内容を書き進めなければ、効果的なアピールは見込めません。そこで、この記事ではESにゼミの活動内容を書く際のポイントを例文付きで解説します。ゼミに入っていない場合に書くことについても取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。

「ES作成ツール」ならあなただけのESが1分で完成します
「ES作成は時間も労力もかかるし大変…」と感じていませんか?ES作成だけでなく、ESの書き直しも時間や労力が必要です。
そんなあなたにぴったりのツールが「ES作成ツール」です!
「ES作成ツール」はESの設問や希望する文字数、そしてあなたが強調したいキーワードを入力するだけで、6万枚以上のESを学習したAIがESを自動生成してくれる便利なツールです。
あなたの強みや経験を魅力的に表現し、企業が求める内容にマッチしたESを瞬時に生成可能ですのでぜひご活用ください。
ESでゼミでの活動内容について聞かれる理由
学生の興味・関心について知りたい
ゼミの学習や研究の内容は場所によって様々です。学生は自分の興味・関心に応じて所属したいところを自ら選び、志願する場合が多いでしょう。
希望したゼミに必ず入れる訳ではありませんが、その場合でも配属先でどのような研究テーマを選んだのかという点には興味・関心が影響するはずです。
つまり、エントリーシート(ES)でゼミについての質問を聞くことで、企業側は応募者の興味・関心について知ることができます。
興味・関心は人柄や仕事のモチベーションにも関連するため、知りたがる企業が多い事柄です。
ゼミの場合、研究の内容が仕事に直接関連するという応募者も少なくないため、そこでの活動について聞かれることが多いのでしょう。
物事に取り組む姿勢を知りたい
学部卒の学生であれば基本的には1年ほど、大学院卒の学生であればもっと長い年月を研究に費やします。
そのため、企業側はゼミでの活動について知ることで、長期的な活動に取り組む姿勢についても知ることができます。
これらは仕事にどのような姿勢で取り組んでくれそうかということを判断するための有用な材料になります。
企業側は採用に多大な時間とコストを掛けているため、内定を出した応募者にはなるべく長く働き続けて欲しいと考えるものです。
それ故に、応募者が長期間の仕事でも真面目に、熱心に取り組むことができそうかという点を重視しているでしょう。
入社後に活かせる知識・スキルを知りたい
ゼミでは専門性の高い研究をするため、それが仕事と強く関連を持っている場合があります。企業や職種によっては、入社前の段階で応募者に一定の専門的な知識・スキルを求めることもあるでしょう。
そのため、ESでゼミでの経験について聞くことで、企業側は仕事に活かせる専門的な知識・スキルをどれほど有しているかということを確認できます。応募者からしても、自身の知識・スキルをアピールできる絶好の機会と言えるでしょう。
専門的なもの以外にも、ゼミでの経験からは活動に対する自主性の高さ、研究には付き物である課題への取り組み方や解決力、論理的思考力などが伝わります。
いずれも多くの仕事で求められる能力であるため、研究と仕事に直接の関連性が無くても、ゼミでの経験は注目されやすいのです。
ESの内容を自己流で1から考えるのは危険です
自己流で1から考えると、時間をかけて作成したESでも、企業が求める方向性と違って最後まで読んでもらえないかもしれません。
そこで、「ES作成ツール」に自動でESを作成させてみませんか?
「ES作成ツール」はES選考を突破した6万枚以上のESを学習したAIがいつでも何度でもあなただけのESを1分以内に自動で作成できる便利なツールです。
あなたがESに入れたいキーワードを入れるだけでAIが自動でESを作成します。
IT業界志望の場合
ゼミ活動をわかりやすく伝えるESの書き方
ゼミや研究テーマの概要と選んだ理由
まずは何を専攻とするゼミに所属し、どのような研究テーマに取り組んだのかという概要を簡潔に述べましょう。そこから専攻のイメージができる場合には、研究テーマだけを説明しても構いません。
また、研究テーマには専門用語が入っていることが多くありますが、それが読み手に伝わるとは限らないため、簡単な表現に言い換えるなど、誰に対しても分かりやすくなるように工夫することが大切です。
次に、そのテーマを選んだ理由を簡潔に説明しましょう。研究の分野に対して、魅力的に感じたことや気になったこと、解決したかった課題などがあるはずです。
なんとなく選んだのではなく、きちんとした理由があってそこを選んだという、ゼミ活動に対して意欲的である姿勢を見せられると良いでしょう。
具体的な取り組み
研究テーマに関して簡潔に伝えることが出来たら、具体的な研究の取り組みを説明しましょう。
採用担当者はゼミでの経験から、主に物事に取り組む姿勢や人柄、スキルを知りたいと考えています。
そのため、ただ取り組みについて伝えるのではなく、取り組みの中で直面した課題、そして課題にどう対処したかということを軸に話を広げられるとより好ましいでしょう。
採用担当者の知りたいことが色濃く表れるこの部分が、最もアピールに有効な場面であると言えるため、時間をかけて推敲することをおすすめします。
経験から得られたものを入社後どう活かすか
ゼミでの経験について具体的に述べられたら、そこで得られたものについて述べましょう。何らかの学びを得たり、伸ばすことができたスキルがあるはずです。
企業は仕事を通してスキルアップし、将来的に会社により大きく貢献してくれる人材を求めています。
得たものを示すということは、経験を通してしっかりと成長していける人材であるというアピールをすることに繋がります。
可能であれば最後に得られたものを入社後にどう活かすかを示し、文章を締めましょう。
ゼミ経験に関する記入欄は、応募者のアピール欄の一つでもあります。そのため、最後までアピールが重要となります。
得たものを仕事で活かすことができるならば、企業にとって書き手はより魅力的な存在に思えるでしょう。

ESを添削しないで企業に提出するのは大変危険です
ESの添削を自分で済ませようとする就活生はとても多いのではないでしょうか?
自分で添削すると誤字・脱字に気づかなかったり、文章が整っていなかったりと細かいところを見落としがちです。
「ES Checker」ならあなたのESを入力するだけで、AIがすぐに項目別に採点し改善案を提案します。
ESを採点し、あなたの強みや価値観を魅力的に伝える改善案を提供しますのでぜひご活用ください。
ESでゼミを伝えるときのポイント
専門用語は使わない
ゼミでは専門分野を扱う関係上、活動について専門用語を用いて説明したくなることもあるでしょう。しかし、ESは読み手が疑問に感じたことをその場で書き手に確認するということはできません。
そのため、どのような人が読み手になったとしても理解してもらえるように内容を書かなければいけません。
専門用語を使わずに別の分かりやすい表現に置換するようにしましょう。
専門用語を用いた方が内容を書きやすいという場合には、簡単な説明を添えるようにすると良いでしょう。
例えば、「採用選考応募者の人柄やスキルを知るための質問用紙であるエントリーシート」というようなイメージです。
分かりやすく書くということはゼミに関する質問に限らず、ES全体を書くうえで意識しましょう。
内容は簡潔にする
ESにおける文章での回答は、基本的には数百文字を要します。すなわち、冗長だと読みにくく、内容を掴みにくい文章になってしまいやすいです。
そのため、内容は簡潔にし、何を伝えたいのかという要点が明確に分かる文章にすることが好ましいです。
簡潔で分かりやすい文章を書く方法として、「PREP法」というものがあります。
これは以下のような展開で文章を構成していくものです。
①Point(結論):「私の長所は○○です」のような最も伝えたい要点
②Reason(理由):①の結論に至った理由
③Example(具体例):①と②について納得させる具体的な事例
④Point(結論 / まとめ):①の要点の表現を変えた再提示
構成が非常にシンプルであるため、話の流れを掴みやすく、要点が分かりやすいというメリットがあります。
自己PRや志望動機など、ESや面接への回答で幅広く応用できるため、おすすめの方法です。
企業が求める人物像を意識する
ESでゼミ経験を書く際のアピール内容、及びそれを裏付ける具体例は企業が求める人物像に合わせることで魅力がより伝わるでしょう。
例えば、「活発で何事にも積極的な人材」を求める企業に「黙々と作業を続けられる」という強みはあまり響かないかもしれません。
そのため、より良いアピールのためには企業研究をしっかりと行い、どのような人材が求められているかを把握しておく必要があります。
企業側は公式サイトや求人サイトで「求める人物像」を明確に提示している場合があります。
そうでない場合には、社員インタビューなどを読んで社風や実際に働く人の人柄を掴むことで求める人物像を推測することができます。
ESの内容を自己流で1から考えるのは危険です
自己流で1から考えると、時間をかけて作成したESでも、企業が求める方向性と違って最後まで読んでもらえないかもしれません。
そこで、「ES作成ツール」に自動でESを作成させてみませんか?
「ES作成ツール」はES選考を突破した6万枚以上のESを学習したAIがいつでも何度でもあなただけのESを1分以内に自動で作成する便利なツールです。
あなたがESに入れたいキーワードを入れるだけでAIが自動で作成します。
(コンサル業界志望の場合)
ESのゼミでの活動内容の例文
100字以内の場合①
ジャーナリズム論のゼミに所属し「ソーシャルメディアにおける情報の拡散と信頼性」について研究しました。情報源が多様化する中、情報の真偽を見極め、信頼できる情報を発信することの意義と重要性を考察しました。(100字以内)
ゼミ活動に関する設問の文字数制限が100字以内と少ないこともあります。テーマ選定の理由や詳しい研究内容までを記載することはできないため、構成としては例文のように、ゼミの専攻や研究テーマを短く述べ、研究内容を大まかに説明する程度で問題ありません。
詳細は面接で深掘りされる可能性が高いため、取り組みの内容や得た学びやスキルに関して、具体的に話せるように準備をしておくことをおすすめします。
100字以内の場合②
地域社会における観光資源の活用をテーマに研究しました。地元企業や自治体との連携を通じて具体的な提案を行い、観光促進策の実現可能性を探求しました。(100字以内)
この例文では端的に研究テーマの説明を行い、取り組みについても具体的に述べられています。取り組み内容が手広いことから、研究への積極性がうかがえる点が印象的です。
①の例文と同様に、100字以内に収める場合はゼミの概要と取り組みの簡単なまとめだけを伝えれば問題ありません。
200字以内の場合①
私は犯罪心理学ゼミで犯罪率減少のための社会的な取り組みについて考察しました。重大事件の加害者は幼少期に置かれた社会環境が劣悪であった場合が多いと知り、犯罪心理学に興味を持ったからです。統計分析やアンケート調査の結果、地域コミュニティが活発な地域では少年犯罪発生率が低い傾向がありました。このことから犯罪は個人の問題だけでなく社会全体の問題であり、青少年を見守る社会気運の情勢が必要であると感じました。(200字以内)
文字数制限が200字以内の文章は依然としてコンパクトですが、100字以内の文章と比べて記載できる内容は増えています。この場合、例文のように、研究テーマを選んだ理由、活動経験から得た学びに関する記載を入れると良いでしょう。
選んだ研究テーマから、企業は応募者の興味・関心や人柄を読み取ろうとします。文字数に余裕があればゼミでの活動を通して自分が学んだことや成長したこともあわせてアピールしましょう。
200字以内の場合②
ゼミでは食品ロス削減をテーマに研究しました。飲食店や消費者へのアンケート調査を通じて、食品ロスの主な原因を分析し、具体的な削減案を提案しました。提案の一つであるメニュー最適化のアイデアは、協力いただいた飲食店で実験的に導入され、廃棄量の減少という成果を得られました。この活動を通して、多様な視点を踏まえた課題解決の重要性と、現場との連携の大切さを実感しました。(200字以内)
この例文では食品ロスについての研究をアピールしており、特に食品や飲食系の業界で効果的な内容となっています。100字以内の場合よりも多くの内容を盛り込めるため、学びを書くことで活かせている点は高評価を得やすいでしょう。
300字以内の場合①
私は人間環境学部のゼミで都市部にありながら豊かな自然環境を維持する街づくりについて研究しました。環境問題が深刻化する中、人と自然が共生できる社会を実現することは喫緊の課題となっているからです。研究ではドイツのフライブルク市の事例から、市民参加型の都市計画の在り方や、公共交通機関の充実、再生可能エネルギーの導入の方法などを考察しました。
研究を通して、人と自然が共生する街づくりには、行政、市民の意識、企業の活動が三位一体となって推進することが重要であると学びました。この研究で培った分析力、問題解決能力、そして人と自然を繋ぐ情熱を活かして、貴社でサステナブルな社会の実現に貢献したいと考えております。(300字以内)
300字になると、研究テーマ、そのテーマを選んだ理由、研究内容、研究で得た学び、それをどう仕事で活かすか、という企業側が知りたいであろう情報を一通り説明する余地があります。研究内容は200字の時よりも少し厚めに記述してOKです。
この例文では理想の社会を実現するために何が必要なのかを研究を通して自分なりに考察できているほか、研究内容と応募企業で実現したいことに関連性があり、企業側に自社との適性をアピールできています。
300字以内の場合②
ゼミでは、地方都市の過疎化対策をテーマに研究しました。特に若者の移住促進に注目し、地域資源を活用した起業支援策の提案を行いました。現地調査では、自治体職員や住民へのヒアリングを通じて、若者が抱える課題を具体的に把握しました。また、他地域の成功事例を分析し、それをもとに独自の移住支援プログラムを設計しました。提案内容の一部は自治体の広報活動に採用され、若者向けのイベント企画にも反映されました。さらに、提案実現に向けた自治体との定期的な会議を通じて、課題解決に必要な合意形成や調整力を学ぶことができました。この経験から、現地の声を反映した解決策を立案する力を養いました。(300字以内)
この例文はテーマや取り組みの説明から、成果と学びを述べられています。①と比べて、企業でどのように活かすかという部分が入れられていませんが、その代わりに取り組み内容をさらに具体化させている部分がポイントです。
企業の業務と関連性があるなど、特に内容を厚くしたい箇所がある場合には、この例文のように優先度の低い項目を省くことも検討しましょう。
400字以内の場合①
現代社会において共働き家庭の増加や核家族化により、親子間のコミュニケーション不足が深刻化しています。そこで私は理工学部のゼミで、遊びを通して親子のコミュニケーションを促進するゲームについて研究・開発しました。
ゲーム開発にあたり、親子へのアンケート調査やインタビューを行い、ニーズを分析しました。開発段階では、実際に親子を対象としたテストプレイを行い、子供の反応や親子の会話内容を詳細に観察しました。また、心理学の専門家やゲームデザイナーと意見交換を重ね、子どもたちの興味関心を高め、親子の共感を生み出すゲームデザインを追求しました。試作品を製作し、親子を対象としたテストを実施した結果、ゲームを通して親子の会話が活発になり、互いの理解が深まったという評価を得ました。
この研究で培った、ユーザーのニーズを分析し、創造的なソリューションを開発する能力は、貴社の事業開発においても活かせると考えております。(400字)
文字数制限が400字以内ともなると、アピール文としての機能を十分に果たせるようになります。具体的な活動内容や研究を通して得たものをしっかりと説明し、それがどう仕事に役立つのか企業にアピールすることを意識しましょう。
また文章が長くなるため、読みやすくするために構成にはより気を遣う必要があります。
構成は「ゼミや研究テーマの概要」と「選んだ理由」から始め、「研究内容」を具体的に述べ、「得たもの」についての話で締めるのが好ましいでしょう。
400字以内の場合②
ゼミでは、環境問題と持続可能な社会の実現に向けた研究を行いました。特に企業の環境への影響を最小限に抑えるための経済的インセンティブを中心に探求しました。企業活動が環境に与える負荷を軽減するために、企業のコスト削減と環境保護を両立させる施策を提案することを目指しました。まず、企業が行う環境負荷の調査を実施し、温室効果ガスの排出量やエネルギー消費量を数値化しました。その上で、環境に優しい技術の導入やエネルギー効率化のための投資に対する経済的インセンティブについて分析し、具体的な施策を提案しました。最終的には、環境対策と経済的利益が両立する企業戦略を提案し、実際に一部の企業に対して提案を行うことができました。この研究を通じて、持続可能な社会づくりに貢献するための実践的な知識と課題解決能力を養うことができました。(400字以内)
この例文では研究の目的と取り組みを重点的に説明しており、深い研究の成果が感じられる内容となっています。
一方で、企業でどのように活かしていくかという部分を少しでも取り入れることができると、より充実した内容になるでしょう。

「ES作成ツール」があなただけのESが1分で完成します
ES作成に何時間も費やしてしまい面接対策までできないと悩む学生は多いです。
そんなあなたにぴったりのツールが「ES作成ツール」です!
「ES作成ツール」はESの設問や希望する文字数、そしてあなたが強調したいキーワードを入力するだけで、6万枚以上のESを学習したAIがESを自動生成してくれる便利なツールです。
あなたの強みや経験を魅力的に表現し、企業が求める内容にマッチしたESを瞬時に生成可能ですのでぜひご活用ください。
ゼミに入っていない場合は何を書けばいい?
ゼミに入っていない理由を書く
ゼミへの所属が必須ではないなどの理由から、ゼミ活動の経験が無く、質問に答えられないという人もいるでしょう。その場合は、記入欄を空欄にはせず、まずはゼミに入っていない理由について書きましょう。
このとき、「興味のあるゼミが無かったから」などネガティブな内容を書くと、消極的な学生に見られ、採用担当者にマイナスの印象を与えてしまうでしょう。
そのため、できるだけ「長期インターンや留学と重なったから」などポジティブな内容を書くことをおすすめします。
ゼミの代わりに取り組んだことを書く
ゼミに入っていない理由を書いたら、それに代わる学生時代の取り組みについて伝えましょう。
企業側がESでゼミについて聞くのは、「応募者の学生時代での取り組みや得た学び」を知りたいということが大きな理由です。
この「企業側がゼミに関する質問で知りたがっていること」を意識し、それに応えられる内容を代わりに書けると良いでしょう。
ゼミの代わりに書ける取り組みの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 部活動
- サークル活動
- 長期インターン
- 留学
- 課外活動
- 資格勉強
- アルバイト
ゼミの経験が無い場合には、上記を参考に、より良いアピールができる題材を選んでみてください。
ESに書くゼミ経験を効果的なアピールにしよう
ESで求められる「ゼミの活動内容」は、そのゼミのことを知りたいのではなく、そのゼミを選び、取り組みをした就活生の性格や能力を知るために設けられているものです。
そのため、ただゼミの概要を書くのではなく、そのゼミを選んだ目的や得た学びを述べることで、企業に自身のことを効果的にアピールできます。
この記事で紹介した書き方や例文を参考に、より関心を持ってもらいやすいゼミ経験を書けるように心がけましょう。