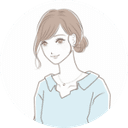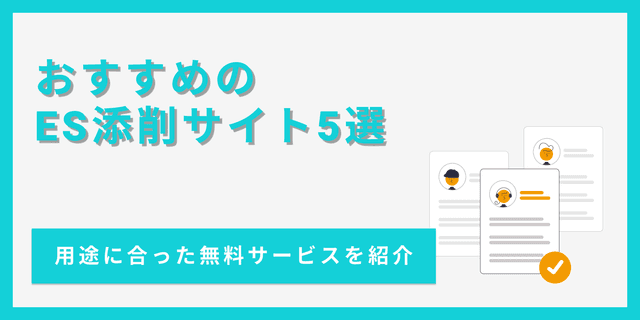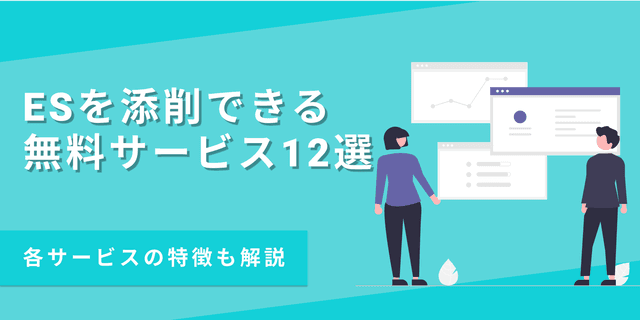完全無料26.27卒必見!
ES作成に役立つおすすめツール3選!
あなたの魅力を最大限に引き出すESがわずか60秒で完成します
あなたのESを入力するだけでAIが即座に採点しフィードバックが受けられます
自己PRとは何かから他者と差別化する方法まで詳しく解説します
ガクチカとは、学生時代に力を入れたことを指す言葉で、就活用語として使われています。
ESに頻出する質問の1つであり、企業が学生のさまざまな要素をチェックするために重要な判断材料となります。その分、どのように作成すればいいのか悩んでしまう学生が少なくありません。
本記事では、ガクチカで研究活動を伝えるメリットや書き方、ポイントについて解説します。アピールポイント別の例文も紹介しているので、ガクチカで研究活動をアピールする人はぜひ参考にしてください。

「ES作成ツール」ならあなただけのESが1分で完成します
「ES作成は時間も労力もかかるし大変…」と感じていませんか?ES作成だけでなく、ESの書き直しも時間や労力が必要です。
そんなあなたにぴったりのツールが「ES作成ツール」です!
「ES作成ツール」はESの設問や希望する文字数、そしてあなたが強調したいキーワードを入力するだけで、6万枚以上のESを学習したAIがESを自動生成してくれる便利なツールです。
あなたの強みや経験を魅力的に表現し、企業が求める内容にマッチしたESを瞬時に生成可能ですのでぜひご活用ください。
企業がガクチカでチェックしているポイント
人間性や自社とのマッチ度
企業は、ガクチカから学生の人間性や価値観、自社にマッチしている人材かを見極めています。
採用にはスキルも大切ですが、人間性や人柄も同じくらい重要な要素です。人間性を確認することで、自社の一員として問題なく業務をこなせるかをチェックしています。
また、新規採用において、自社とのマッチングを重視する企業は少なくありません。マッチしていない人材を採用した場合、入社後の短期離職のリスクが高くなります。コストをかけて採用をしたにもかかわらず、入社後すぐの退職は企業にも大きな損失です。
そのため、自社に馴染めるのかという視点においてガクチカは重要な判断材料となります。
ポテンシャル
ポテンシャルとは将来性を意味する言葉であり、採用後の活躍を期待して採用を決める企業も非常に多いです。ガクチカは、学生のポテンシャルを判断するための材料にもなります。
企業はガクチカから、経験によって学んだことや今後どのように活かせるのかを見て、学生のポテンシャルを判断しています。また、困難を乗り越えて成長した経験は、企業で活躍できる可能性を見極めるポイントの1つです。
そのため、ガクチカを作成するときは、困難を乗り越えるために模索した点やアイデアについてを記載することが大切です。
論理的に伝える力
論理的に伝える力は、社会人としても非常に重要な能力です。ESにおいても論理的に説明できていない場合、仕事ができないとマイナスに捉えられ、採用に影響を及ぼす可能性があります。
ガクチカに記載されている文章がわかりやすく伝えられているのであれば、企業は学生に論理的に伝える力があると判断し、有能な人材と考えます。
論理的に伝えるためには、CREC法を取り入れて作成することがポイントです。CREC法は、結論から伝えるため、分かりやすく論理的にかつ簡潔に伝えることができると言われています。
下記の表に沿ってエピソードをまとめることで、簡潔で説得力のある内容になるでしょう。
<CREC法>
- C 結論(Conclusion)
- R 根拠(Reason)
- E 事例(Example)
- C 結論(Conclusion)
ESの内容を自己流で1から考えるのは危険です
自己流で1から考えると、時間をかけて作成したESでも、企業が求める方向性と違って最後まで読んでもらえないかもしれません。
そこで、「ES作成ツール」に自動でESを作成させてみませんか?
「ES作成ツール」はES選考を突破した6万枚以上のESを学習したAIがいつでも何度でもあなただけのESを1分以内に自動で作成できる便利なツールです。
あなたがESに入れたいキーワードを入れるだけでAIが自動でESを作成します。
IT業界志望の場合
ガクチカで研究を伝えるメリット
努力をわかりやすく表現できる
研究活動で取り組んできたことは、学業の集大成ともいえます。大学で勉強してきたことを具体的に言語化しやすいため、努力をアピールしやすいメリットがあります。
学生のなかには、ガクチカが思いつかずに無理やりエピソードを探すこともあるかもしれません。研究活動に本気で力を入れてきた学生なら、無理なく説得力のあるガクチカを作成できるでしょう。
ガクチカで努力をアピールするためには、困難に立ち向かったことについて明確にする必要があります。研究活動を行ったエピソードだけでは魅力が十分に伝わらないため、研究のプロセスで起こった問題や課題をしっかりと記載することが必要です。
研究活動を説明する際は、目標を明確にし、達成するための取り組みや課題を説明しましょう。発生した問題から、自分なりの対応や努力を詳しく説明することで、頑張った経験が伝わるガクチカになります。
研究内容=実績として判断される
応募先企業に研究内容を活かせる場合、研究内容=実績として判断されることがあります。特に、理系学生で専門的な研究をしているなら、研究内容と実際に業務がつながる可能性があるため、実績があれば評価につながります。
もちろん結果だけでなく過程も大切なので、研究の課題や困難から得た学びを伝え、企業にどのように活かしていくのか伝えることが大事です。
研究活動は専門性の高い分野のため、専門スキルを求めている企業にとって求められる人材です。研究内容と業務がつながっているのなら、入社後すぐの活躍が期待できることもあり、就活が有利に進められます。
結果が出てなくても過程をアピールできる
結果が出ていない場合でも、研究活動であれば過程をアピールしやすいメリットがあります。
研究活動では結果はどうであれ、どんな研究内容でも自分なりに考えた行動の記録が残ります。そのため、問題解決のために起こした行動を説明しやすいのです。
ガクチカで結果が出ていない研究活動を記載する際は、失敗から得た経験について詳しく伝えることがポイントです。分析や努力について自分なりに取った行動を説明することで、企業は学生の人柄やポテンシャルを見ることができます。

ESを添削しないで企業に提出するのは大変危険です
ESの添削を自分で済ませようとする就活生はとても多いのではないでしょうか?
自分で添削すると誤字・脱字に気づかなかったり、文章が整っていなかったりと細かいところを見落としがちです。
「ES Checker」ならあなたのESを入力するだけで、AIがすぐに項目別に採点し改善案を提案します。
ESを採点し、あなたの強みや価値観を魅力的に伝える改善案を提供しますのでぜひご活用ください。
ガクチカで研究をアピールするときの書き方
①結論
ガクチカで研究をアピールするときは、まず結論を記載します。ここでいう結論は、研究内容を指します。取り組んだ研究テーマを簡潔に伝えることで、企業はどのような内容なのか理解できます。
研究について書くときは、難しい表現にならないようにしましょう。例えば「私は大学で、SNSの利用とその心理について研究をしています。」のように、研究が専門外でも理解できるよう複雑な説明は避け、かみ砕いた表現にすることがポイントです。
動機
次に、研究を始めた動機や意義を説明します。なぜ研究を始めようと思ったのか、研究テーマを選定した理由などについて記載しましょう。
企業は動機や意義から、学生がどのようなことに興味を持つのか、学生の価値観、ポテンシャルなどを見ています。研究の動機が明確でない場合、企業は学生の研究にかける熱意が読み取りにくくなるので注意してください。
目標・困難
研究テーマ、動機の次は、研究の目標を述べましょう。目標とは、求めている成果やどのような結果を目指していたかの記述を指します。目標は具体的に表現し、数値化することでわかりやすく伝えられます。
目標の次に困難の紹介です。研究活動中はすべてがスムーズではなかったはずです。研究の過程で直面した課題や困難のなかで、印象強く残っている辛かったことを記載しましょう。困難は大きなものがいいわけではなく、小さなトラブルでも問題ありません。
取り組み・結果
努力した結果を伝えるために取り組みの説明を行います。立てた目標に対して、どのように取り組んできたのかを記載しましょう。
また、困難を述べただけでは頑張りが伝わらないので、どのように乗り越えたかを説明します。何を考えてどのような対応をしたのかを述べることで、レベルの高いガクチカになります。
取り組みで得られた結果を伝えることで、企業は入社後に活躍できるかイメージしやすくなります。結果に説得力をもたらすには、取り組み前と後の心境の変化を記載することがポイントです。
学び
最後にまとめとして、研究活動から学んだことや今後の展望を記します。学びや気づきは重要であり、採用担当者は学生が経験から何を学び、これからどのように活かしていくのかを注目しています。
経験から学んだことを業務に活かせるガクチカであれば、能力やスキルが備わっている学生だと採用担当者に判断してもらえるでしょう。
ESの内容を自己流で1から考えるのは危険です
自己流で1から考えると、時間をかけて作成したESでも、企業が求める方向性と違って最後まで読んでもらえないかもしれません。
そこで、「ES作成ツール」に自動でESを作成させてみませんか?
「ES作成ツール」はES選考を突破した6万枚以上のESを学習したAIがいつでも何度でもあなただけのESを1分以内に自動で作成する便利なツールです。
あなたがESに入れたいキーワードを入れるだけでAIが自動で作成します。
(コンサル業界志望の場合)
【アピールポイント別】ガクチカで研究をアピールする例文
計画力
私は大学3年次に、〇〇の研究活動に注力しました。〇〇については子供のころから興味があり、いつか研究をしてみたいと思い、〇〇が学べる現在の大学を選びました。
私の所属する研究室では、1つのテーマにつき2ヵ月以上の研究期間がかかるという課題がありました。目標達成のためには計画力と実行力が必要だと考え、実験計画を立てることにしました。まず、日々の目標を設定し、それを達成するための計画を練りました。また、他の研究者の方々とコミュニケーションをとり、自分の考えを伝えることで、より良い結果が得られるよう努めました。
その結果、1ヵ月で研究を終えることができ、目標としていた以上の成果を得ることができました。就職後も目標達成のために所要時間を考え、計画性を発揮して結果を出していきたいです。(350字以内)
最初に何の研究なのかを伝えることで、採用担当者が内容について理解しやすい構成になっています。研究の動機や目標を達成する取り組みについても簡潔にまとめられています。
また、結果についても数値化して表しているのでわかりやすくなっています。
計画力は社会人にとって必要なスキルなので、魅力的な強みと評価されやすいです。入社後の活躍を記載することで、入社後に活躍できるイメージを持ってもらいやすいでしょう。
粘り強さ
私は、学生時代〇〇の研究開発に取り組みました。研究を始めた当初は、技術的な知識や経験が乏しいため、成果を出せませんでした。しかし、諦めることは選ばず、持ち前の粘り強さを発揮して、基礎から鍛え直そうと決意しました。着実なステップアップのため、研究にかける時間を増やし、基礎研究を何度も実施しました。失敗したときは課題を洗い出し、その都度担当教官や研究室のメンバーに相談し、解決することを繰り返しました。
その結果、研究をやり遂げることに成功しました。この経験で、コツコツと努力し続けることや、根気強くやり遂げることの重要性を学びました。社会人になると、うまくいかないことが多いかもしれません。しかし、私の粘り強さを発揮して貴社に貢献できる社員を目指したいです。(350字以内)
目標達成のために自分の強みをどのように活かしたのかを具体的に記載しているため、学生の粘り強さが伝わる例文になっています。専門用語もなく、研究が専門外の採用担当者でも理解しやすい仕上がりになっています。
研究活動のガクチカは他の学生と差別化しやすいため、採用担当者が興味を持ってくれる可能性が高いです。粘り強さのアピールはポテンシャルがあると捉える企業もあるので、ガクチカを作成するときにおすすめのアピールポイントです。
協調性
私は、大学3年次に運動リハビリテーションの研究をしました。作業療法士になることが目標なので、研究テーマに選びました。
研究を始めた当初は、研究がうまくいかず、1人の力で続けることに限界を感じました。そこで、研究室の仲間と協力し、1つの目標に2チームで成果を出すことにしました。仲間と協力して課題解決に取り組むことで、研究に対するモチベーションも上がりました。
その結果、学会発表や論文執筆など、様々な活動に挑戦することができました。この経験から、協調性を持って物事に取り組むことの大切さを学びました。
作業療法士の仕事では他のスタッフとの連携が重要だと考えています。貴社に入社後は協調性を活かして企業活動に貢献していきたいです。(350字以内)
作業療法士の選考に向けたガクチカの例文です。協調性をうまくアピールした例文になっています。
仕事も1人ですべて対応することはできないため、協調性やコミュニケーションスキルといった社会人に必要なスキルをアピールできています。
また、志望動機とつながりのあるガクチカになっているので、説得力が増しています。強みの活かし方についても応募先に必要なスキルだとわかりやすいため、採用担当者に良い印象を与えるでしょう。
論理的思考力
私は大学で、SNSの利用とその心理について研究をしています。SNSの利用で精神面に影響を及ぼした経験があり、SNSが与える影響について気になり始めました。
研究では選択式の質問紙による調査方法を考えましたが、オンラインツールを利用するか街頭調査をするかで意見が割れました。どちらかの方法を選ぶと、選ばれなかったメンバーの士気が下がると考え、双方が納得するために両方の調査方法を実施するといった、お互いの意見を取り入れた解決策を提案しました。
その結果、さまざまな意見や有効性の高い回答を得ることができ、お互いのメリットをうまく取り入れることができました。このように、私は課題に直面したときでも、柔軟な対応で解決策を見出すことができます。
社会人になると多くの課題が待ち受けていると思いますが、課題の本質にいち早く気づき、解決のために行動を起こしていきたいです。(400字以内)
論理的思考力は面接や選考の過程で伝わるものなので、アピールするときは論理的思考力を言い換えてアピールしましょう。
今回の例文では、論理的思考力を課題の本質に早く気づける強みとして言い換えています。他にも、分析力や課題解決力も、論理的思考力の言い換えとして使える強みです。
また、論理的思考力を伝えるには、課題の解決策を論理的に道筋を立てて説明することが大切です。例文では課題に対しどのように考え、何を行動したかが明確になっているため、論理的思考力があると判断されるガクチカになっています。
課題解決力
私は、以前からアプリ開発に興味があり、近年増加している「〇〇アプリ」を研究テーマに選び注力しました。
しかし、実験でなかなか仮説どおりの結果が出ず続けることに苦労しました。結果が出ない原因を追究するために、実験結果が出る度に教授に相談したり、研究室の仲間に意見をもらったり、新たな情報を得るために何度も参考文献の確認も行い、新たな課題と解決策を洗い出し、繰り返し実行に移しました。
その結果、7回目の実験でようやく納得のいく結果を出すことができました。この経験により、起こっている問題を解決するためには、視野を広げ、試行錯誤を繰り返すことの大切さを養うことができたと感じています。
入社後に課題に直面しても、課題点を探り問題解決に向けて試行錯誤できる社員を目指し、アプリ開発に貢献したいと考えています。(350字以内)
研究のガクチカでは、課題解決力を伝えやすいメリットがあります。企業にとっても課題解決力が強みの学生は、仕事の成果につながりやすいと感じ、ポジティブな印象を受けるでしょう。
また、問題解決のために周囲を巻き込むことで、コミュニケーションスキルの高さもアピールできています。最後は応募先と絡めた学びを記載しているところも、高評価につながります。

「ES作成ツール」があなただけのESが1分で完成します
ES作成に何時間も費やしてしまい面接対策までできないと悩む学生は多いです。
そんなあなたにぴったりのツールが「ES作成ツール」です!
「ES作成ツール」はESの設問や希望する文字数、そしてあなたが強調したいキーワードを入力するだけで、6万枚以上のESを学習したAIがESを自動生成してくれる便利なツールです。
あなたの強みや経験を魅力的に表現し、企業が求める内容にマッチしたESを瞬時に生成可能ですのでぜひご活用ください。
ガクチカで研究をアピールするときのポイント
専門用語は使わない
研究活動では多くの専門用語がありますが、ガクチカで多用するのは避けましょう。採用担当者がわからない場合は、研究内容が入ってきづらく評価が悪くなる恐れがあります。
ガクチカを作成する際はかみ砕いた表現を意識して、専門外の人にも伝わる表現をすることが大切です。しかし、普段から専門用語を使い慣れている場合、無意識のうちに使ってしまう可能性があります。
そうならないために、ガクチカを作成した後に、一度研究を専門外の人に確認してもらうと安心です。また、どうしても専門用語を使用する必要がある場合は、補足として簡単な説明を入れるようにしましょう。
企業でどのように活かせるかを記載する
ガクチカの重要なポイントは、企業で活かせる強みやスキルを伝えることです。企業は学生が自社にとって、採用するメリットがあるのかを判断する必要があります。
ガクチカで企業に活かせる強みをアピールするには、企業の仕事内容と経験からの強みがつながっていることを示します。アピールポイントがずれてしまわないように、企業研究を念入りに行ってから作成することをおすすめします。
志望動機とつなげる
ガクチカと志望動機がつながっていると、根拠のある志望動機になり説得力がプラスされます。研究内容が志望業界とつながっている場合は、研究経験を志望動機にするのがおすすめです。
その場合、応募企業の業界や業務に対する基本的な知識があることもアピールできるため、採用側の印象は良くなるでしょう。
研究内容と志望業界が完全に一致していなくても、研究から得られた強みを志望動機とつなげてアピールすると好印象につながります。
異なっている場合は、業界を志望した理由や企業を応募した理由について具体的に説明できると採用側も納得できるでしょう。
研究経験をガクチカにする際のよくある質問
研究活動に実績がなくてもアピールしていい?
採用担当者はガクチカに成果や実績は重要視していないため、実績がなくても自信を持ってアピールしましょう。大事なのは過程であり、人間性や価値観を見極める内容であるかが重要です。
実績がない場合は取り組んだ内容を重点的に記載し、活動によって得た学びをしっかりと記してください。続いて、経験からの学びを業務にどのように活かすかを記載しましょう。
研究活動が途中の場合でもいい?
研究が途中の場合でも、過程を具体的に記載できるのなら差し支えありません。前述したとおり過程が大切なので、研究活動の意義や困難、乗り越えたときの行動を記してください。
現時点での研究成果と、今後どのような結果を求めているのかを記載すると、採用担当者が研究内容についてわかりやすくなります。
研究内容がほかの学生と被ってるときはどうする?
研究内容が被っていても、研究への取り組み方や困難の乗り越え方まで同じことはないはずです。活動経験は1人1人異なるので、研究内容の被りは気にする必要はありません。
過程の違いで個性がでるため、自分の取り組んできた姿勢をアピールしていくことが重要です。研究活動で意識したことや、学んだことについて自分なりの考えを加えることで、さらにオリジナリティのあるガクチカになるでしょう。
研究活動のガクチカはさまざまなスキルのアピールが可能!
研究活動はガクチカでさまざまなスキルや強みをアピールできます。他の学生との差別化もできるため、研究活動の経験があるのなら積極的にアピールしていきましょう。
研究は専門的な内容が多いため、ガクチカにする際はわかりやすい言葉選びが大切です。伝え方を工夫するだけで、レベルの高いガクチカの作成ができます。
たとえ研究に実績がない場合や途中の段階でも、研究活動の過程は十分なアピールポイントになります。自分自身が得た経験や取り組んだ姿勢について、本記事を参考にしながら作成してみてください。